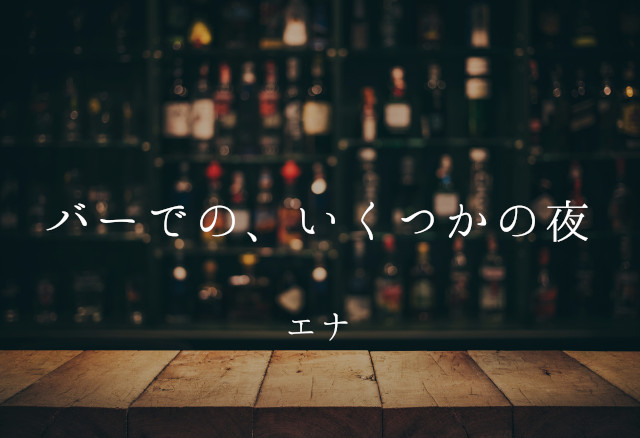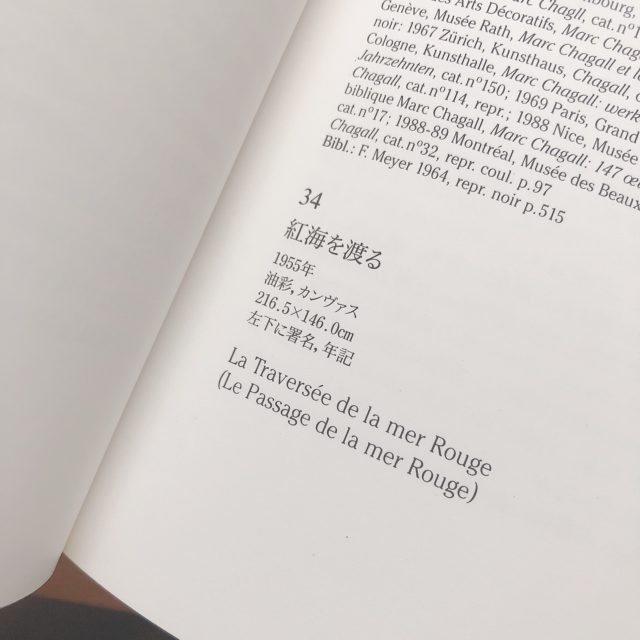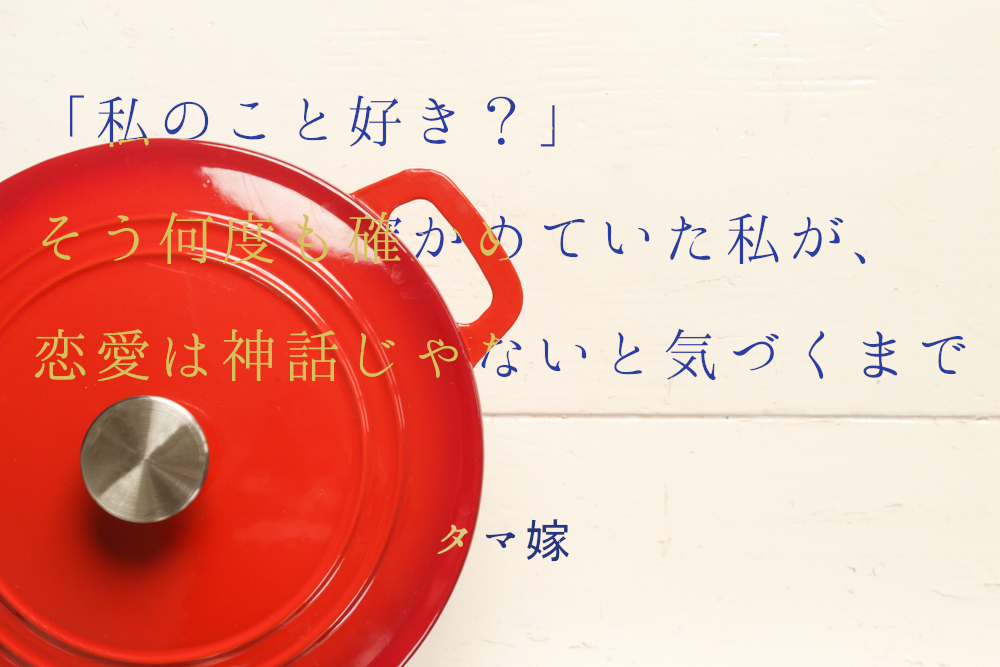Contents
果たしてその恋の終わりを受け入れられるだろうか
恋の終わりに鉛筆でしっかり線を引いて「今日で終わり」とできればいいのだけど、実際は振り子のように「忘れられない」と「もう大丈夫」を行ったり来たりしながら気持ちに折り合いを付けていく。
気持ちの波に翻弄されながらも、彼女たちはその恋が終わったことを知っているのだ。気持ちはなかなか追いつかないが、どのようにすべきか頭では分かっている。
その一方で恋の終わりを受け入れられず、いつまでも一人相撲のように恋愛を続けてしまうケースもある。心が通じ合った瞬間を永遠のものであるかのように錯覚し、いつまでも気持ちを引きずってしまうのだ。人の気持ちが移り変わることを上手く飲み込めずに。
わたしにもそんな経験がある。
恋の終わりを受け止められなかったこと。続きを待っていたこと。
そしてそれを断ち切ったのは、相手の目だった。
その時のことを書いてみようと思う。
傲慢な恋愛の終わり
その日「別れよう」とメールが送られてきた。
正確には覚えていないが、簡潔な短い文章だった。夏の終わり、日が落ちる少し前、一人暮らしの小さな部屋には西日が射していた。
わたしはあまり動揺していなかった。「ふうん」と軽く流すような感じだろうか。ショックを受けていないわけではなく、ただ本気だと思っていなかったのだ。
どちらかというと、わたしはその恋に強気だったのだろう。事の重大性にも気付かず「また謝ってくるだろう」と呑気に構えていたのだ。
「また」というからには以前もあったということだ。別れを切り出されるのは初めてだったが、喧嘩をすることは度々あった。仲は良かったのだが、それなりに喧嘩をしては「許してほしい」と頭を下げられるようなことが度々あったのだ。
このように書くと彼が許されないことをやってきたかのように思われるかもしれないが、そうではない。彼はいたって誠実で、大事に至るような喧嘩はなかったように思う。喧嘩の原因は「肉の赤身が好きか、脂身が好きか」というようなくだらないことばかり。そんな平和な日々を送っていたものだから、二人の仲は順調だと、そう思っていた。
二人で過ごす日々は満ち足りたものだった。やさしい彼は言葉で愛を伝え、行動で愛を示し、目や表情で愛を語った。愛に深い人で、愛される幸せを存分に感じさせてくれる人だった。不安など何もなかった。
おそらく別れを切り出すまでには彼の中で色々な葛藤があっただろう。でも、わたしがそれを感じたことは一度もなかった。メールをもらうその時まで、彼の気持ちに変化が訪れていることに全く気づかなかったのだ。
更にわたしは愛されていることに自信を持っていた。彼のやさしさにあぐらをかき、慢心していた。愛されない日が来ることなど想像すらできなかったのだ。
だからこのメールだってきっとそう。数日後には戻ってくる。心からそう信じていた。痛みを知らない年だったとはいえ、なんと傲慢で愚かだったのだろう。
彼のいない世界は傾いている
彼から別れを突きつけられたものの、心の中ではまだその恋が続いていた。今回のこともいつもの喧嘩だろうと高を括っていたものだから、「ごめんね」と謝ってくるのを毎日ひたすら待ちわびていたのだ。
しかし、今日もメールは来ない。
次の日も、その次の日もメールは来ないのだ。
次第に不安になってくる。
少しずつ、今回は様子が違うことが分かってくる。
一日中一緒にいて、いつも手を繋いでいたものだから、右手が手持ちぶさたになった。行き場のない右手はとても心細く、世界が傾いてしまったかのようだった。
バランスが取れない。地面は平行だろうか。真っ直ぐ歩けない。もうしゃがみこんでしまいたい。
このような感覚は初めてだった。道の真ん中で目眩がした。
メールをもらってから二週間後のことだった。
そして知る。恋が終わったことを
そんなある日、彼に遭遇した。自動販売機の光だけが煌々と輝く、薄暗い路地での出来事だ。彼は数人の友人たちと建物から出てきたところだった。その時、幸か不幸か偶然その場を通りかかったわたしと目が合ったのだ。
背筋が凍った。
これまでに見たことのないような目だったのだ。怒りもなければ悲しみもない。動揺するわけでもない。何もない目。何もなかった目。出会ったことすらなかったような、知らない人のような目だった。
彼の目に映ったのは、自動販売機とゴミ箱、それらと同列のわたし。
彼の中でわたしは無機質なモノでしかなかった。その目はわたしが恋人だったことは疎か、血の通っている人間だということさえ忘れているようだった。
怒りとか悲しみとか、感情が伝わる目だったのならまだ救われたのかもしれない。でも、そこにすら至らない。彼の恋人だったわたしは、既に存在さえないものとして扱われているようだった。
自分が透明になったかのようだった。
「もうとっくに終わっていたんだ」
そのことにようやく気づいた瞬間だった。
目を凝らすことで、目を曇らせている
さて、わたしは以前恋愛サイトでお悩み相談をしていたことがあり、たくさんの相談をいただいた。その中には「彼は私のことを好きだと思いますか?」というような、相手の胸の内を知りたいという内容のメールがいくつも届いた。
恋する女の子たちは、好きな人の一挙一動に意味を見出そうとする。一つひとつの言葉に何かサインはないだろうかと考え、相手の挙動に目を凝らし、その裏を読もうとする。胸の内を知りたいがあまり、必要以上に推察してしまうのだ。
でもどんなに言葉の意味を推察しても、どんなに行動に意味を見出そうとしても、それは一つのシーンに過ぎないのではないだろうか。
実際に自分のことを思い返してみても、大人になればなるほど不本意ながらも社交辞令を言えるようになり、愛想笑いもできるようなった。それなりに本音と建前を使い分け、波風を立てないよう振る舞うことができるようになったのだ。それならば本心を隠せるようになったかというと、残念ながらそういうわけではない。
本質的な思いは「目」に表れるのだ。
目は飾ることも、取り繕うことも、偽ることもできない。
思い返してみてほしい。自分を愛してくれている母の目を。あるいは恋人の目を。愛しい者を見る目は穏やかで愛に溢れている。たとえ衝突することがあったとしても、その目は真剣な眼差しをしているだろう。怒りをたたえていようと悲しみをたたえていようと根本的には愛があり、相手を大事にすべき者だと認識して向き合おうとしているからだ。
「目は口ほどに物を言う」の真理
恋する女の子たちは微かな光を見逃さず、それを必死に握りしめ、折れそうな心をなんとか支えようとしている。小さな希望のかけらを集めて一喜一憂するのは恋の醍醐味。そうやって楽しむのも素敵な恋愛だと思う。
でも、本心が知りたいなら、目が語ることを信じてみてはどうだろう。
目から感じるものをまっすぐ受け止めてみてはどうだろう。
その目は愛しい者を見る目だろうか。
その目にあなたの姿は映っているだろうか。
そこにこそ、あなたの知りたいと思うことが映し出されているのではないだろうか。
「目は口ほどに物を言う」とはよく言ったものだ。
伝える手段もテクノロジーも発達し、検索すればたくさんの恋愛テクニックやハウツーが溢れているこの時代で、本心は目にこそ宿っている。こんな使い古されたシンプルな言葉にこそ真理が詰まっているのだ。